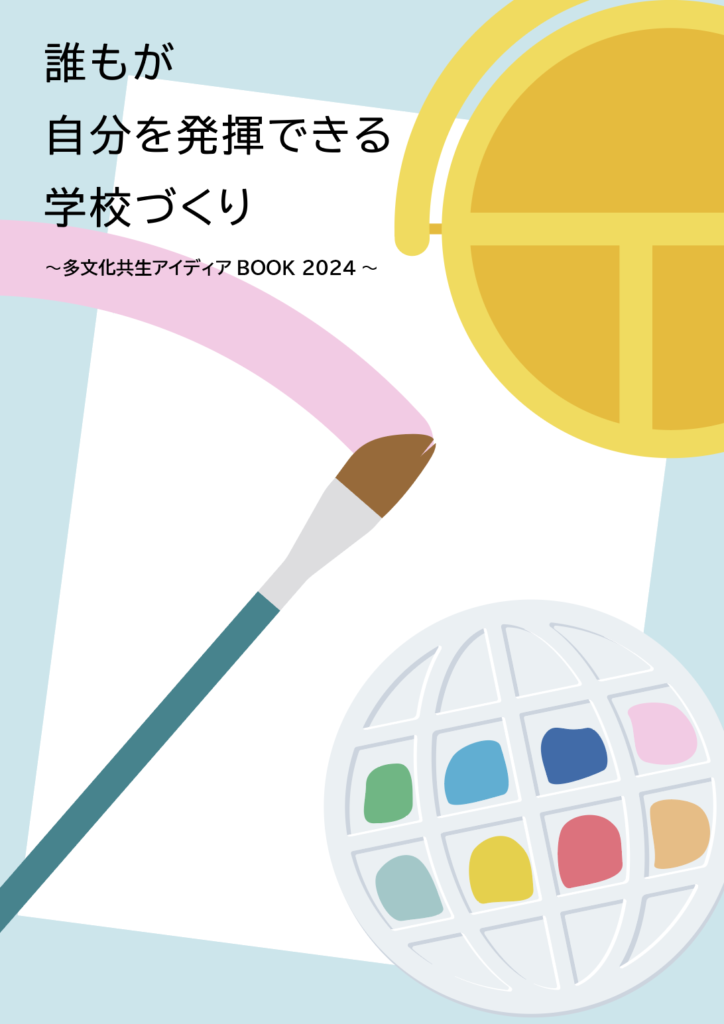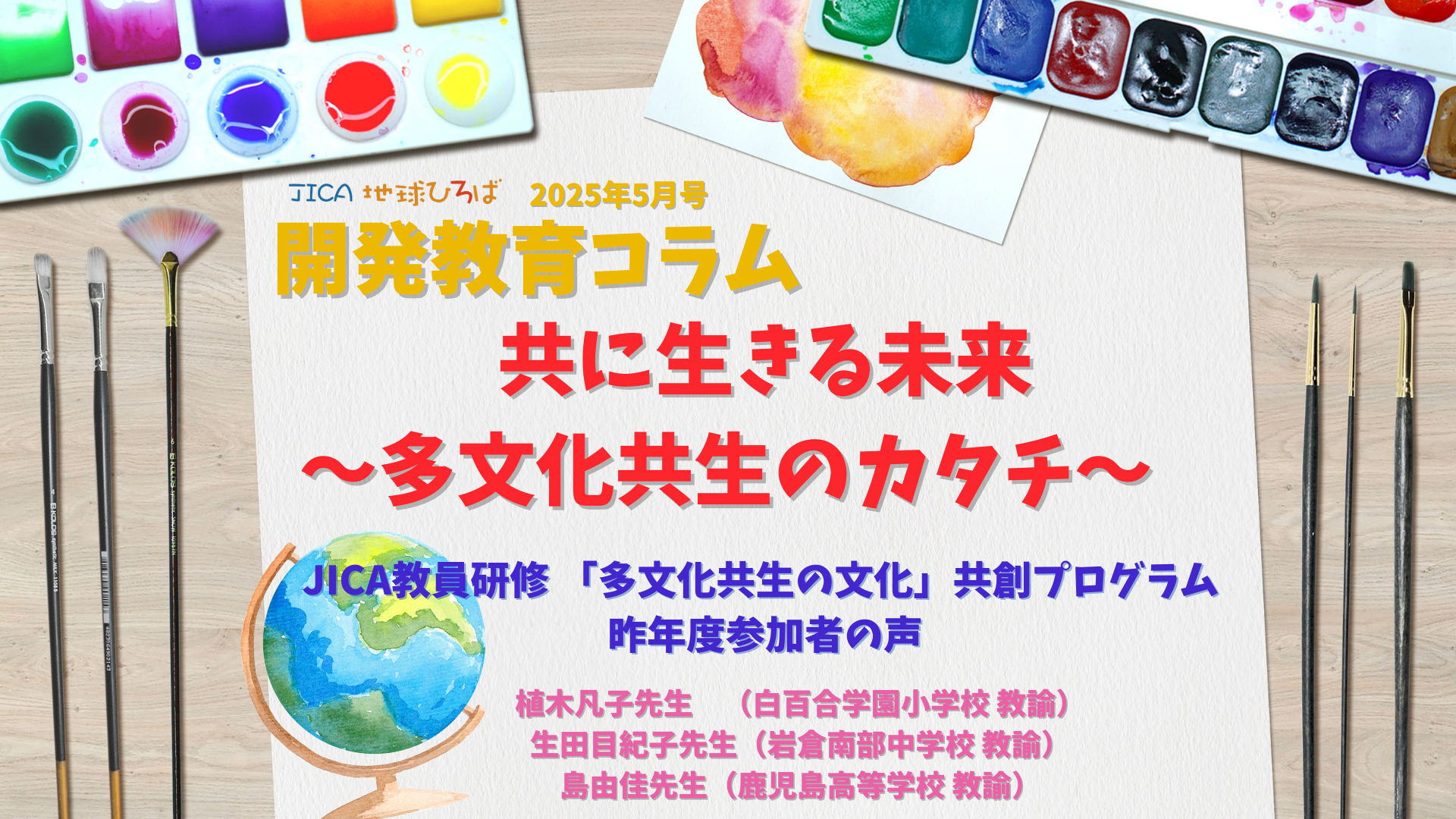
JICAでは毎年、多文化共生に関する取り組みを行う小・中・高校、特別支援学校に勤務する教員を対象に、「多文化共生の文化」共創プログラムを実施しています。 今回のコラムでは、昨年度にJICA横浜(※今年度より地球ひろばで実施)を舞台に開催された同プログラムに参加した3名の先生方に、プログラムで得た学びや、その後の取り組みについてお話を伺いました。
▼目次
- 1. 「多文化共生」への第一歩
- 2. 過去から今、そして未来へとつながる学び
- 3. 「多文化共生の文化」共創プログラムから教室へ 〜出会い、ひらく多文化の扉〜
- 4. 子どもたちの未来のために、今できること
語り手
2024年度JICA「多文化共生の文化」共創プログラム 参加者
.jpg)
植木 凡子 先生
白百合学園小学校 教諭

生田目 紀子 先生
岩倉市立南部中学校 教諭

島 由佳 先生
鹿児島高等学校 教諭
1. 「多文化共生」への第一歩
Q. プログラムに参加したきっかけを教えてください。
植木先生: 私学の図工の授業を担当する教員として、整った環境の中で、子どもたちに良質な材料を使って作品づくりや活動を行う日々を過ごしてきました。しかし、物質的に恵まれた環境であるがゆえに、「良い材料だから良く見えるだけではないか?」という疑問が芽生え、本来の「表現の本質」について考えるようになりました。
そんな中で、開発途上国など物質的に制約のある環境で図工を教えるとしたらどんな授業ができるのか、という問いがきっかけとなり、異なる文化や物質的に制約のある地域など、自分とは異なる環境の教育現場への関心が芽生えました。
また、コロナ禍で海外渡航が難しい状況の下、JICA東京の「教員のためのSDGs研修」に参加し、他校の教員たちと交わることで、教育が社会や環境と密接につながっていることにあらためて気づき、自分の視野がいかに学校という枠の中に閉じこもっていたのかを痛感しました。その経験をきっかけに、積極的に外に目を向けるようになっていたときにこのプログラムを知り、参加を決意しました。
生田目先生: 本校がある愛知県岩倉市では現在、全体で16か国17言語の多国籍の児童生徒が在籍しており、本校は、全校生徒の約15%の外国につながる生徒が在籍しています。
学級担任や特別支援担任を経て、日本語適応教室の教員として「岩倉市日本語・ポルトガル語適応指導教室」に赴任しましたが、前任校では通用してきた学年・学級経営がここではうまく機能せず悩む同僚の姿がありました。組織としての多文化対応力向上を図れば、多国籍多数ならではの特性をプラスにすることができる学校になるのではないか、そしてそれが外国につながる生徒だけではなく、日本人生徒も含めた生徒全員のウェルビーイングにつながると考え、全国で同じように取り組む先生方と交流し、多様な意見や視点を得たいと思うようになりました。
このプログラムへの参加を通じて、自分自身が学び、考えを深める中で、この適応指導教室や生徒たちに還元できることがあるのではないかと思ったことが、参加へのきっかけでした。
島先生: 私にとって、このプログラムが初めてのJICA研修への参加となりました。以前から鹿児島県内の高校生と日本語学校の留学生との交流活動を行っていましたが、活動の意義が見出せなくなり、自信を失いかけていた時に、このプログラムの存在を知りました。多文化共生に取り組む全国の先生方と出会い、励ましやアドバイスをもらいたいと思い、参加を決めました。
鹿児島県の日本語学校はまだあまり地域社会に認知されておらず、周囲の人の理解も十分ではありませんが、そこで学ぶ留学生たちは近い将来、日本で働き、私たちと共生していく存在です。だからこそ、高校生が将来一緒に働くことになる彼らへの理解を深め、偏見を持たずに関われるような場を作りたいと考え、プログラムに参加しました。
2. 過去から今、そして未来へとつながる学び
Q. プログラム中に特に印象的だった学びや気づきについてお聞かせください。
植木先生: プログラムの中で特に印象に残っているのは、「言葉」について深く考えるきっかけをたくさんいただいたことです。言葉には限界があり、同じ言葉でも受け取る側によって意味や印象が異なります。だからこそ、言葉は単なる伝達手段ではなく、相手との関係性や文化背景を含んだ「生きたもの」なのだと実感しました。
研修の中で、「気持ち悪い」などといった言葉に傷ついた経験を持つ子どもたちの話を聞きました。その言葉が日本語であっても外国語であっても、人を深く傷つけてしまうことに変わりはありません。そのような事例を通して、「自分は日本人として、普段から言葉を本当に大切に使えているだろうか?」と問い直すようになりました。言葉は相手を思いやる姿勢や文化が込められたものとして、これからもっと丁寧に言葉と向き合っていきたいという思いが強くなりました。
生田目先生: このプログラムに参加して、自分がこれまで漠然と考え、取り組んできた「多文化共生」についての見方がよりクリアになりました。当初は「多文化共生」という言葉を、外側に向かう視点、つまり「自分が外に向けて何かをすること」と漠然と捉えていました。しかし、研修を通じて他者のルーツについて触れる中で、その視点が自分自身の内側に向かう体験がありました。自分のルーツについて話すことで、自分が日本人であるとはどういうことか、また日本に生まれても国籍が異なる人がいることなど、これまで意識してこなかった「自分という存在」についてあらためて考えさせられました。
自分の内側に意識を向けることは、自分自身を大切に考えるということ。子どもたち、特に外国につながる子どもたちは、日本の社会の中で生きていく上で、自分のルーツや文化的背景で苦労したり、つらい思いをすることがあると思います。そうしたときに、自分自身のルーツや背景を理解し、自分を支える知識や知恵を持っていれば、たくましく生きる力につながるはずです。だからこそ、まずは教員自身が自らのルーツを見つめ直し、それを子どもたちに伝えていくことが、生きる力を育む教育につながると感じました。
島先生: 私も生田目先生と同じように、JICA横浜の海外移住資料館の見学を通じて得た「ルーツ」に関する気づきが印象的です。個人的なことですが、カナダに移住した親戚のことをこれまで「移民」として捉えたことがなく、単に「カナダに移り住んだ親戚」として見ていた自分に驚きました。
また、日本から海外に移住した先祖たちが、現地で差別やさまざまな困難に直面しながらも、たくましく生き抜いてきたことを知りました。その経験は今、日本に来ている外国人の方々が直面している課題と重なる部分があり、同じように苦労や差別が存在しているのだという視点を持つことができました。こうした歴史や経験を学ぶことで、過去の困難をどのように乗り越え、解決に向けて歩んできたのかを理解し、今の多文化共生の課題に対しても新たな見方や考え方を得られるのではないかと感じています。自分の先祖がどのような状況でどんな苦労を乗り越えてきたのか、より詳しく調べたいと思うようになりました。

3. 「多文化共生の文化」共創プログラムから教室へ 〜出会い、ひらく多文化の扉〜
Q. プログラムに参加後のご自身の意識の変化や、学校での実践についてお聞かせください。
島先生: 本校は外国につながる生徒も少なく、校内で多文化共生の文化づくりを目指した特別な取り組みは行われていません。しかし生徒たちは卒業後、外国人労働者と共に働く社会に出ていきます。そのため、高校在学中に外国籍の人々と接する機会を外部と連携してつくりたいと考え、同じ鹿児島県の小学校からのプログラム参加者の先生との連携した取り組みを始めました。その先生の勤務校には県内唯一の日本語教室があり、そこで実施されるイベントに高校生も参加させていただくことになりました。高校生がブースを出し、外国につながる子どもたちと関わることで、実際のふれあいを通して学ぶ機会にしたいと思っています。
また、地域の日本語学校の先生と話す中で、進路や面接指導に苦慮しているという声を聞きました。日本語学校の先生方は人手も少なく手一杯のため、留学生と年齢が近い高校生だからこそできることがあるのではないかという話になりました。今後、留学生の進路相談や面接練習などを通して、高校生と日本語学校に通う留学生の交流ができないか検討中です。また、今年から英語クラブ(ESS)を立ち上げ、まずは同好会レベルで活動を始め、いずれはクラス単位に広げていけたらと考えています。留学生の多くは19~20歳で、高校生にとっては年齢が近いけれど、「なんとなく怖い」という先入観があるようです。まずは「同じ人間である」という気づきから始めて、次に文化の違いを学び、理解を深めていく。このプロセスを大切にしながら、高校ではまず「知り合う・関わる」経験の機会を提供したいと思っています。
生田目先生: 私はプログラム参加後、名古屋にあるネパール人学校への視察を行いました。ネパールで教育に携わっていた先生方との情報交換を通じて、日々の指導で感じていた疑問や工夫のポイントについて具体的なアドバイスをいただくことができ、今後の活動にも大いに活かせると感じました。また、ブラジル人学校への視察も実施することができました。昨年度は、ネパール人学校とブラジル人学校の両方と関わることができた点が大きな成果かなと思います。
さらに、学校の文化祭にて「外国につながる生徒有志たちのルーツ別パフォーマンス発表」を実施しました。出演するかどうかは生徒の自己判断を尊重し、希望する生徒に出演してもらいました。その中で、インターネットを通じた情報共有の影響か、各国のダンスや音楽が似てきていることに気づきました。観覧者からは「もっと各国の伝統的な文化を見たかった」との声もありましたが、そうした声がステレオタイプにつながることもあると感じています。今後は発信する側と受け取る側の双方の思いを丁寧に汲み取り、対話を通してお互いの気づきにつなげていくことが、「多文化共生」の文化づくりに向けた大切なプロセスであり、私の役割でもあると考えています。
植木先生: これまでにJICAの教員向け研修に2回参加し、「学校で抱えている問題は1人で抱え込まず、対話をしながらチームで取り組むこと」の大切さに気づくことができました。本校は外国につながる子どもが少ない学校ではありますが、多文化共生の文化をどう学校に根づかせていくかを考える中で、自分ひとりの視点では限界があり、他の先生方と連携していくことの重要性を感じています。
また、教科横断的な授業の可能性も感じています。たとえば、家庭科でお茶の淹れ方を学習した時期に、理科の先生は摘んできた茶葉から自分で日本茶ができるのか試してみた、という話を聞きました。その話をきっかけに図工では、おもてなしの演出(お茶やお菓子)を各国の文化を想像しながら工作する授業を実施しました。まだ表面的な学びではありますが、そこから社会や外国語など他教科とのつながりを広げていける可能性を感じています。
さらに、JICA東京の「教師海外研修」を通じてつながった先生方と、ブラジル人が多く住む群馬県大泉町のブラジリアンプラザを訪問しました。実際に現地を訪れ、人とつながることで、新たな学びや「もっと知りたい」という意欲が湧いてくることを実感しています。私自身が学校の外に出て、多くの人とつながり、学びを深めていくことで、学校や子どもたちにさまざまなことを還元していけるのではないかと思っています。

4. 子どもたちの未来のために、今できること
Q. プログラムへの参加を検討している教員へのアドバイスやメッセージをお願いします。
生田目先生:現在、私がいるような学校の現状は、きっとこれから日本全国どこの学校でも直面することになるでしょう。だからこそ、「多文化共生は自分の学校にはまだあまり関係ない」と感じている先生こそ、このプログラムに参加する価値があると強く思います。特に、「自分にはまだよくわからない」と感じている方ほど、こうした場で多くを学べると思いますし、今の日本の教育現場には、そうした目線をもつ先生がますます必要とされています。敷居を高く考えず、どんな立場の先生も、ぜひ参加してほしいです。
学びを教室の中だけにとどめず、地域の中で子どもたちや保護者と関わることが、多文化共生の理解をグッと深めてくれます。たとえば私は、地域の外国人向けの食品店でよく買い物をしますが、保護者や生徒と偶然出会うときは挨拶したり立ち話をしたりすることもあります。また同僚の先生方もその食品店にお連れして、生徒たちのバックグラウンドへのより深い理解につなげる取り組みをしました。
学校の外こそ多文化共生のリアルは広がっています。少しだけ勇気を出して、そのような世界に足を踏み入れてみることで、きっと新しい気づきや視点が得られるはずです。
植木先生: 本校は、まだ生田目先生のご所属校のような状況には至っていませんが、先生のお話を伺っていて、日本の教育現場は今後確実にそうした現実に直面していくのだろうと強く感じました。電車に乗っていても、当たり前のように周囲に多くの外国人の方がいるように、これからの学校はもっと柔軟に地域・社会とのつながりを大切にしていかなければならないと痛感しています。
でも、やはり一番大切なのは、いま目の前にいる子どもたちと丁寧に向き合っていくことだと思います。このプログラムでは、それぞれの現実と真摯に向き合う先生方と出会い、直接お話できる貴重な機会があります。
自校の状況にかかわらず、「目の前の子どもたちを大切にしたい」という思いがある先生であれば、どなたでもぜひ参加していただきたいです。参加することで、自分の学校の良さや、新たな視点にも気づくことができるはずです。迷っている先生がいらっしゃれば、ぜひ子どもたちのために一歩踏み出してみてほしいです。
島先生:私はこのプログラムで、同じ鹿児島内から参加したもうひとりの先生とつながり、一緒に活動を行うことができました。参加前は自分の活動に自信を失いかけていましたが、同じ志を持つ仲間が県内、そして全国にできたことはとても心強かったです。
先生方には、あまり構えすぎず、気軽な気持ちで参加していただきたいと思います。中には「国際理解に関する研修かな?」と感じる方もいるかもしれませんが、「多文化共生」と「国際理解」は少し見ている方向性が異なります。「多文化共生」という言葉にピンと来ない方や、よくわからないと感じている方こそ、ぜひこのプログラムに参加してほしいです。きっと新たな視点が得られると思います。

★ JICA「多文化共生の文化」共創プログラム 成果物のご紹介
このプログラムでは、参加者が自身の所属先で「多文化共生の文化」を育むために今後取り組みたい活動をアイディアとしてまとめ、それらを共有する冊子を作成します。
過去の成果物一覧は、こちらからご覧いただけます。
編集後記
3人の先生方のお話をお伺いして、「多文化共生の文化」とは完成形があるものではなく、”問い続けること”そのものが実践であると感じました。小さな違和感に気づいたり、自分にとっての当たり前を見直してみたり、そうした日々の積み重ねが、共に生きることにつながっていくのかもしれません。
今年度もJICAでは「多文化共生の文化」共創プログラムの参加者を募集しています。目の前の子どもたちの未来のために、一歩踏み出してみませんか?
みなさまのご応募をお待ちしています!
▼ JICA地球ひろば 開発教育メルマガのご案内
国際理解教育・開発教育に役立つ情報を効率的にキャッチできるメールマガジン。
JICAの研修やイベント・セミナーの情報やおすすめの教材、コラムなどを毎月配信しています。