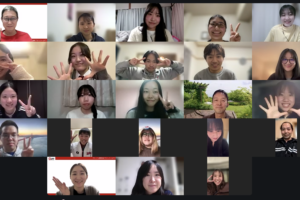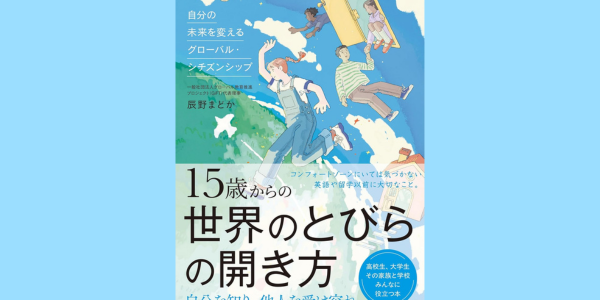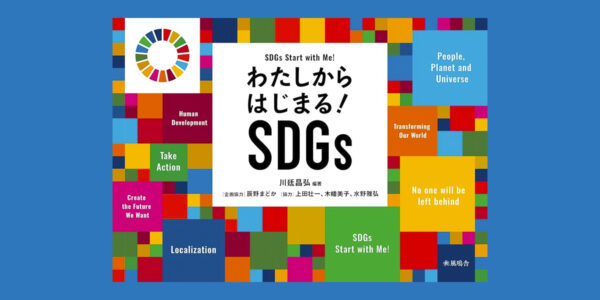【レポート】JICA教員研修「多文化共生の文化」共創プログラムを実施しました。
GiFTが運営事務局を務めるJICA「多文化共生の文化」共創プログラムを、10月4日・5日・25日の3日間にわたりJICA市ヶ谷で実施しました。
ファシリテーターはGiFT代表理事の辰野まどか。全国から集まった16名の教員が、3つの問いを軸に対話を重ね、自分たちの学校や地域でできるアクションを考えていきました。
*なぜ、今、「多文化共生の文化」が必要とされているのか?
*私たちが共創したい文化とは何か?
*その文化を育むために、私たちができることは何か?
以下、プログラムの様子をご覧ください。
1日目:出会いと気づきの連続
初日は、「なぜ、今、多文化共生の文化が必要とされているのか?」の問いとともに、「多文化共生の文化」の共創につながる各自の取り組みと課題の共有からスタートし、JICA地球ひろばの展示見学や多文化共生ワークショップの体験へと続きました。
午後には新宿区立愛日小学校を訪問し、ベトナムの日本人学校でのご経験をもつ福成俊之副校長先生からお話を伺いました。グローバルな視点と地域教育のつながりを実感し、「持続可能な国際理解教育」について深く考える機会となりました。



2日目:違いを紡ぎ、共に生きることを考える
2日目は、一般社団法人Enjie代表の矢野デイビット氏を講師に迎え、「お互いの『違い』の意味をゆっくり紡いでみる」というテーマでご講演いただきました。矢野氏と参加者の対話の中で、矢野氏は次のように語られました。
「子供たちは日本の未来とよく言われます。しかし、人を育てる先生たち、みなさんが未来そのものです!そう信じています。みなさんが日本の未来です!」
この力強いメッセージに、参加者は大きな勇気と励ましを受けました。
午後には、「未来に向けて共創したい多文化共生の文化とは?」「多文化共生の文化がある学校とは?」「その文化を作るためにどんなことができるか?」について対話を重ねました。
2日間のプログラムを通して参加者は、「多文化共生」とは国籍や人種の違いだけでなく、地域、家庭、そして一人ひとりの中に存在するものだとあらためて実感しました。
また、他者と共に生きるためには、まず自分自身の文化を理解し、相手への想像力をもって“違い”を尊重することが大切だと強く感じる時間となりました。「多文化共生の文化」づくりには正解がなく、日々の実践を重ねながら互いに寄り添い、最適解を見出していくプロセスなのだという学びが生まれていました。



3日目:アイディアをカタチにする
最終日の研修では、参加者それぞれが考えた「学校で多文化共生の文化を創るための具体的なアイディア」を共有。仲間からのコメントやフィードバックを通して、多様な視点や新たな可能性が次々と生まれました。
「授業のあり方を見直すきっかけになった」「地域や保護者とのつながりを強めたい」など、参加者の想いが一層具体的になっていく様子が印象的でした。
3日間のプログラムを通じて、参加者は多くの対話を重ねながら、自分の思いを仲間と共有し、支え合う時間を過ごしました。研修を終えた参加者からは、こんな声が寄せられました。
「たくさんの気づきとアイディアをもらった。もやもやもあるけれど、明日からできることを少しずつ始めていきたい。」
「子どもたちが『理解されない』と感じる瞬間を減らしたい。両手を広げて迎える先生でありたい。」
「前回の研修以降、生徒に少し優しくできたと感じる。学び続けることの大切さを実感している。」
「志を同じくする仲間と夢を語る楽しさを味わえた。」
互いの考えを受け止め、夢を少しずつ形にしていく勇気とつながりを実感できた3日間となりました。

次のステップ:「多文化共生アイディアBOOK2025」へ
今後、参加者は自分のアイディアをブラッシュアップしていきます。
それらのアイディアは、プログラムの成果として『誰もが自分を発揮できる学校づくり ~多文化共生アイディアBOOK2025~』にまとめられます。
多文化共生の文化を育むためのヒントやアイディア、そして先生方のリアルな熱い想いが詰まった一冊が、全国の教育現場に新たな視点とインスピレーションを届けることでしょう。
・2025年度「多文化共生の文化」共創プログラムについてはこちら
・過去の成果物は下記リンクより閲覧いただけます
2024年度:『誰もが自分を発揮できる学校づくり ~多文化共生アイディアBOOK2024~』
2023年度:『誰もが自分を発揮できる学校づくり ~多文化共生アイディアBOOK2023~』
2022年度:『誰もが自分を発揮できる学校づくり ~多文化共生アイディアBOOK2022~』